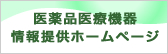保健医療の現場に漢方薬が取り入れられて二十年以上たちます。
漢方薬が本当に効くのか、という議論は、明治時代に西洋医学が採り入れられたときから始まり、現代まで続いています。
私の世代の薬剤師(卒後二十年)の薬科大学のカリキュラムは薬品の合成が中心で漢方薬の効き目に関することはほとんどなく、薬草に関する講義は和漢薬名、西洋生薬名と科名とその有効成分を含む部位の和名、ラテン名を暗記する私にはつまらない授業でした。なかなか生薬名が覚えられないのをみかねた先輩からリンドウ科のラテン科名「ゲンチアナシー」は「林道を歩いていると現地の人の穴をみつけた」とか、藤圭子の唄の替え歌で「白く咲くのはリリアシー(ユリ科)、赤く咲くのはパパベラシー(ケシ科)」と覚えなさいと教わり、大笑いしたことだけが思い出でした。
そんな程度の漢方知識しかなかった私が本当の漢方に接したのは、きみがよ薬局高橋省哉先生との出会いでした。西洋薬は一つの病気に一つの薬が一対一対応する明確さがありますが、漢方では葛根湯が風邪に用いたり、肩こりに使ったり、また風邪という病気に麻黄湯、桂枝湯などと病気と薬に一対一対応しないのが不思議で、きみがよ薬局高橋省哉先生の門をたたきました。そのときの先生の答えは、「漢方薬は、『隋証療法(ずいしょうりょうほう)』といって、『証(しょう)』に隋(したが)って病を判断し、薬を選択する、同じ患者であってもその『証』を診る人の漢方理論によっても薬の選択に違いが出る。土を焼いた器をイメージしてみなさい。食べ物をのせれば食器になるし、花を生ければ花器にもなる」とのことでした。
『証』とは患者の病に対抗する力と病の強さが戦い合い、そのとき現れる症状で、病の進行過程と密接に関連する漢方概念であることと教わりました。漢方薬を使いこなすには、『証』を診る力と経験が重要で、西洋医学のように、科学的に病気を解析できないところがあり、『学』というより『術』に近いものかもしれないとも教わりました。あまりにも哲学的なので、頭の悪い私には先生のように漢方を極めるのは無理と思いながらも、先生のお話をお聞きするのを楽しみに、お宅にお伺いしたり、先生の講習会を受講しておりました。漢方薬はそれを選択する人の技量で効果が違うため、薬そのものの効き目を科学的に検証しようという研究が進行しています。
薬の効き目を確かめる方法に二重盲検(もうけん)法があります。医師も患者もその薬が本物か偽薬か分からないようにして客観的に効果を調べる方法です。その方法によっても漢方薬の効き目が証明されています。しかしながら私の漢方観では、科学的に効き目が証明された漢方より、何々流とか○○派と称されて、処方を選択する人によって処方に違いが出る、人と人とのふれあいが感じられる『漢方』のほうが好きです。長く研鑚しその道を極めた『漢方』もその人間の上に完成されたものであるならば、その人間の死によって終焉を迎えねばなりません。
石巻薬剤師会、宮城漢方研究会で数多くの薬剤師に漢方を教えていた、高橋省哉先生も今年7月急逝され、「きみがよ漢方」も先生の命と一緒に天に昇ってしまいました。教えを受けたものにとって痛恨の極みです。ご冥福をお祈り申し上げます。